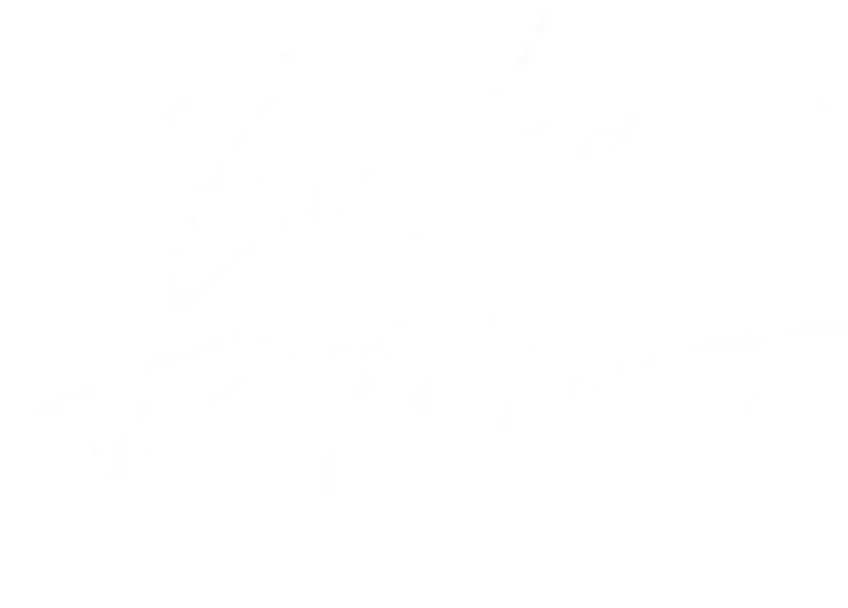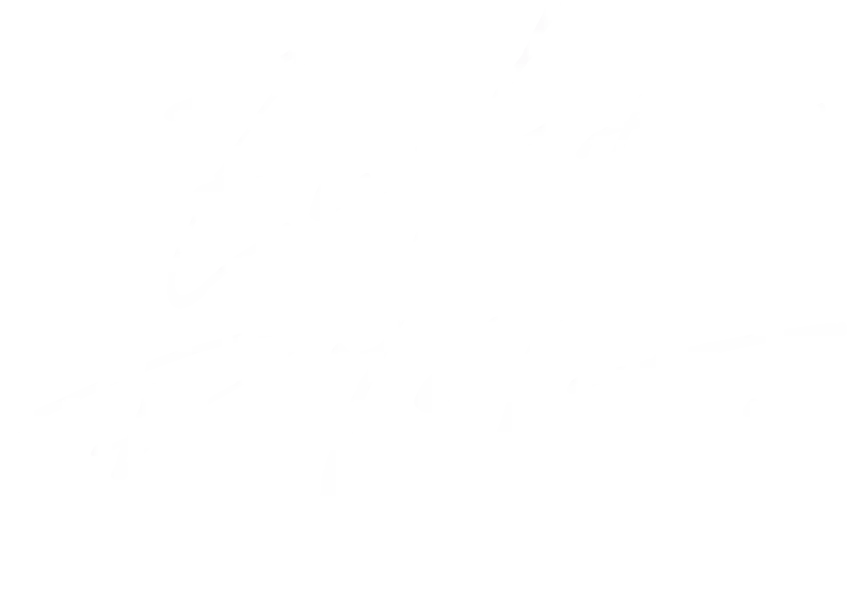Updated 2025.07.14
「赤い金」と呼ばれる希少なスパイス、サフラン。ユーカリオのパエリアに贅沢に使われるこの宝は、料理に独特の風味と色彩を添える唯一無二の存在です。
大分県竹田(たけた)市。こんなにも便利な社会になったのに、いまだに秘境と呼ばれ、「たけだ」と間違えられることもしばしば。日本のサフラン生産量の8割以上を占める名産地だということも、あまり知られていません。暗い室内で花を咲かせる「竹田方式」というユニークな栽培方法は、実に121年(2025年時点)もの歴史を刻んでいます。
この竹田の宝を育てているのが、「お金、大好きなんですよ!」と屈託なく笑う専業農家の長谷川さんです。そのインパクトに最初は驚くかもしれません。でも、言葉の裏には、農業と地域への深く熱い想いが隠されていました。竹田の地に彩りを加えるのはサフランだけではなく地域に生きる人々。長谷川さんの探求の原点と、そこから広がる世界の豊かさに迫ります。

簡単に明かす、サフラン栽培の奥義

「竹田式」と呼ばれる栽培方法。一般的な路地栽培とは異なり、まるで洞窟のような暗く涼しい小屋で花を咲かせます。かつては防空壕も使われたそうです。
「この小屋はね、天井が4メートルもあるんですよ。しっかり空間を作って熱を遮断して、洞窟みたいな状態を目指すんです。そうすると、サフランの花がゆっくり開いていくから、ひとつひとつ丁寧に摘み取れるし、作業効率もぐんと上がります。」
一見、昔ながらの知恵に思えるこの栽培には、驚くほど科学的な根拠があります。サフランの命である香り成分サフラナールと色素成分クロシンは、日光と湿度に非常に弱いからです。この特別な小屋は、日中の強い光を遮り、竹田特有の冬の夜間の高い湿度を巧みに利用することで、大切な成分を分解から守り、高濃度な成分を保てるのです。
「海外のものは路地で栽培するから、日中に花を摘むと、その時点でもう成分がどんどん分解されてしまう。でも、うちはつぼみの状態で収穫して、そのまま乾燥させる。だから、品質が全く違うんですよ。」と長谷川さんは語ります。その言葉通り、国際的な品質基準ISO3682(サフランの主要成分含有量に基づく品質等級)においても、竹田のサフランは常に最高グレードを誇ります。
しかし、長谷川さんの探求心は伝統の製法を守るだけにとどまりません。

「サフランはね、根っこが張る範囲(根域)がすごく小さい植物なんです。だから、土の中の養分を分解してくれる『補助者』、つまり微生物の力がとても大切。その補助者がたくさんいる場所、それがサフランにとって育ちやすい環境なんです。竹田の中でも、この土地が、たまたまそういう場所だったんですね。」
長谷川さんは、かつて他地域でサフラン栽培が根付かなかった背景には、土壌微生物の働きに加え、土地特有の湿度や日当たり、風の流れといった複合的な環境要素が大きく関わっていると考えています。
さらに、この適地に関する情報や、栽培方法など一部の農家の中だけで共有されていたかもしれない、と長谷川さんは語ります。
「なんでみんな、もっとサフラン栽培を広げないんだろうって、ずっと不思議だったんです。もしかしたら、希少性を売りにするために、情報をあまり外に出さなかったのかもしれない。でも、それじゃあサフランの認知度も上がらないし、誰も知らないまま終わってしまう。良いものは、みんなで使ってこそ価値が出るし、地域も豊かになるはずなんです。」
信念を形にするかのように、長谷川さんはサフラン栽培に適した土地を自ら開拓する挑戦も続けています。
「最初はね、まだ土に微生物が馴染んでいないから、なかなか調子が上がらなかった。でも、もともとある良い畑が支えてくれるから、焦らずじっくりやりますよ。」
最高の品質を引き出すため、葉が完全に枯れるまで球根にエネルギーを蓄えさせる――その収穫時期の見極めも、長年の経験と観察の賜物です。土地の力を信じ、時間をかけて向き合う姿は、まさに大地との対話そのものです。


「農業」という哲学
長谷川さんの畑には、サフラン以外にも珍しく色とりどりの野菜が元気に育っています。そこには、彼の農業哲学が鮮やかに映し出されていました。
「多くの人は、自然と戦おうとしがちでしょう?例えば、一生懸命ビニールハウスを作ったりして。でもね、戦う相手がちょっと違うんじゃないかな。自然は仲間なんです。自然を味方につけること、それが俺たちの武器であり、知恵なんですよ。」
そう言って長谷川さんは、日焼けした顔で太陽のように笑いました。ま、まぶしー!

彼が実践する農業とは、自然との「戦い」ではなく、「共生」と「活用」にあります。土、水、地形、気候、そして風の流れに至るまで、その土地のすべてを徹底的に読み解き、野菜たちが最も心地よく、のびのびと育つ環境をデザインする。それはまるで、大地を知り尽くした「リアル風水師」のような、緻密で大胆な戦略です。谷から吹き込む清涼な風や、季節によって移ろう日差しの角度、川から立ち上る豊かな湿気。これら土地の声を読み解き、野菜たちが健やかに成長するための「道」を、自らの手で切り拓いてきました。
その象徴とも言えるのが、畑に壁のようにそびえ立つ岩塊です。長谷川さんがこの地に来た当初は荒れ放題の竹林でしたが、丹念に切り開くと、阿蘇の火砕流によって運ばれたという巨大な火成岩が姿を現しました。崖のような岩に生い茂る竹をを整備する作業は、想像を絶する労力だったはず。「ここは俺の庭。いつかはこの大きな岩をくり抜いて、そこでサフランを育てるのも面白いかもしれないね!」と、その構想は尽きることがありません。この広大な岩場の抜根作業をほとんど一人でこなしたというのですから、とんでもない体力と情熱の持ち主です。

長谷川さんの畑は、まるで好奇心と発見に満ちた「実験室」のようでもあります。イタリアの料理人との出会いがきっかけで栽培を始めたピクルス用のきゅうり、星形が愛らしいズッキーニ「ステラ」、そして日本ではなかなかお目にかかれない西洋ネギ「トロペア」や「セルバチコ」など、まるでヨーロッパの朝市に迷い込んだかのような、珍しくもパワフルな野菜たちが生き生きと育っています。
「テスト栽培するなら、最低でも1000株は作らないとね。それくらいやらないと、その野菜の本当のことは見えてこないでしょう?」
「なんでこうなるのか、その理由が分からないと、やってる意味があまり感じられないんですよね。」
彼の尽きない探究心と、それを支える強靭な体力。畑を歩きながらその場で様々な野菜を味見させてもらうと、一つ一つの野菜が持つ鮮烈な風味と凝縮されたパンチ力に、心が揺さぶられます。例えば、葉ニンニクを一口かじれば、力強い香りと粘りが口いっぱいに広がり、次に味わったハーブ「セルバチコ」は、ゴマのような香ばしさと花の蜜のような優しい甘みが複雑に絡み合い、先ほどのニンニクの風味を一瞬で吹き飛ばすほどの衝撃。これぞ「美味しい」の原体験。素材そのものが持つ力だけでジェットコースターのように感覚を揺さぶるなんて。食のエンタメとしての可能性をダイレクトに感じました。






みんなにおいしいを感じてもらいたい。

「お金持ちじゃなくても、誰もが『うめぇ!うめぇ!』と食べれるものがあった方が、世の中ずっと面白いじゃないですか。そうやって、もっともっと美味しいものを、みんなに届けたいですよね。」
この温かく力強い願いが、「お金、大好きなんですよ!」という端的な言葉で表現されていたのですね。一連の体験を通して、すとんと腑に落ちました。同じ想いです!ありがとうお父さん!
「サフランはね、正直なところ、手間がかかる割には、大きな儲けには繋がりにくいんです。でもね、この竹田のサフランを無くしてしまうのは、ものすごく簡単。『辞めた』って、たった一言で終わってしまう。でも、もし一度辞めてしまったら、この地で今のレベルまで復活させるのに、それこそ120年という途方もない時間が必要になるかもしれない。だからこそ、ちゃんとその価値を理解して味わってもらえるように、僕らが頑張らないといけないんですよね。」
長谷川さんの探求は、「ものはどうやってできるのか」「世界はどんな風に繋がっているのか」という、私たちの根源的な好奇心を刺激し、探求することの面白さを改めて教えてくれます。食材の背景にある物語、生産者の知恵と愛情、そして雄大な自然の摂理。それを知ることで、私たちの毎日の食卓は、どれほど豊かで、味わい深いものになるでしょうか。

この地域では毎年、秋分の日に伝統的な秋祭りが開催されます。
「祭りはね、ただワイワイ楽しむだけじゃなくて、神様に感謝を伝え、その年の収穫物を捧げる、とても大切な場なんです。」
サフランがこの地で育つのは、単なる環境要因だけでなく、こうした大いなるダイナミズムがあってこそ。生命の根源と向き合う営みは、まさに本質的なものです。
これだったら農業は絶対楽しくなる。そう強く思いました。これこそが、極めるべきひとつの道「農道」だ!

食の感動が紡ぐ、地域の未来
長谷川さんの農業哲学は、ユーカリオが提供したい「食と体験」の中心にあります。彼が丹精込めて育てる野菜や121年の歴史を刻むサフランは、単なる食材ではありません。「美味しいって感動させられるかが勝負」という言葉通り、深い知恵と物語、自然との共生が生み出す、かけがえのない「体験のデザイン」そのものです。
ぜひ、竹田を訪れ、そこで育まれた最高の食材と、その背景にある壮大な物語を体験しに来てください。きっと、あなたの食への好奇心は新たな扉を開き、日常がより一層、味わい深いものになるはずです。
私たち「EUKARYOTE(ユーカリオ)」は、「食・仕事・自然とのつながり」を軸に、互恵的な共生を実践・創造する場です。わっちゃんのような地域の宝となる生産者の方々と共に、食を通じて「すごい!」という感動や知的な驚きを共有し、競争ではなく協調による豊かな社会を創造していきます。
text & photograph: Tomokazu Murakami